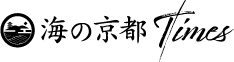天然の要塞、舞鶴湾。山をくりぬいたように入り江が入り組み、湾口の両側にある高い山からは外洋が見渡せる。120年前の明治34年には海軍鎮守府が置かれ、大陸からの脅威に備える国防の拠点となった。しかし、海辺で暮らす人々にとって舞鶴湾は「宝の海」であり、京都の漁業の発信地として発展した歴史はあまり知られていない。城下町の海辺には吉原という小さな集落がある。海と生きた生活史を深掘りすると、そのルーツは6000年前の縄文時代にまで行き着いた。
舞鶴・吉原 城下の漁民は開拓者
海と生きる

京都の近代漁業 発祥の地
静かな運河の両脇に漁船が並ぶ。この風景が雑誌に載ったのを機に、近年は外国人がカメラを手に押し寄せる撮影スポットになっていた。路地裏は車1台が通れる程度。夕暮れには魚を焼く匂いが漂う小さな集落だが、実はここが、京都の近代漁業の発祥の地だった。
「ここは、宝の海だ」
ここで生まれ育った鷲坂光男さん(88)を訪ねた。伊佐津川沿いにある倉庫には、沿岸漁業で使うあらゆる漁具が所狭しと並んでいる。刺し網に底引き網、ナマコ用のケタ網に延縄・・・・・・。15歳から父と漁に出たという鷲坂さんは「遠出しなくても湾の中で年中なにか捕れた。漁場には手こぎの舟ですぐ着ける。ここは宝の海だ」と語り、網を整えながら昔話を聞かせてくれた。
小さな集落に600人の専業漁師が
川から供給される栄養も豊かで、舞鶴湾には多くの魚が卵を産みにやってくる。春はシロメ(イワシの子)を追ってサワラやスズキも入ってくる。刺し網でクロダイやコチも捕れる。夏場はシラサエビの値が良かった。秋はイカやサワラ、冬は延縄でハモ、アナゴ。「海底を少し掘ったらトリガイやアサリが一斗缶いっぱい捕れたよ」。日本海側の冬は北西の季節風で荒れるが、山に囲まれた舞鶴湾は波の心配がない。船の上で網をたぐるだけでいいから、潜水漁をする人はいなかったという。集落に市場があったので売り歩く必要もない。鷲坂さんは若い頃に底引き網漁船に乗って隠岐の島まで出たが、働く時間が長いので湾内の刺し網漁に戻った。安定した生活がおくれるとあって、全国から吉原に移り住む人がいたそうだ。半農半漁が主流の時代に、専業漁師が600人もいたという。
1600年の籠城戦で大活躍
来る者を拒まない気質は、漁民としてのルーツにあるのかもしれない。
そう聞いて、舞鶴市の田辺城資料館に向かった。舞鶴の歴史を調べてきた吉岡博之館長は、戦国時代の絵図を広げた。時は1600年。田辺城にいた細川幽斎(藤孝)は関ヶ原に向けて進む西軍に城を取り囲まれながらも、わずか500人で籠城を決意する。絵図はその模様を描いている。
この時に大活躍したのが吉原の人たちだった。当時は城下町の北端、れうし(漁師)町と書いてある海辺で暮らしていたが、籠城が始まると、彼らは深夜に海からこっそり城に入り、兵士らに魚や食糧を届ける役割を果たしたのだ。天皇の勅命により1カ月半の籠城戦が終わったのは関ヶ原の合戦の3日前。1万5000人の大軍は参戦できず、徳川家康が率いる東軍が勝利した。籠城戦の手柄として、細川は城下の漁民に領内で自由に漁ができる特権を与えたのだった。
れうし町→吉原町へ
ただ、籠城絵図の「れうし町」には家がない。吉岡さんは「漁民は東南アジアのような掘っ立て小屋を並べて暮らしていたのだろう」と話す。江戸時代には戸籍を寺が管理するようになるが、それまでは自由に住む場所を変えられた。田畑を持たぬ漁民は土地に縛られず、海を渡ってどこにでも行けたが、田辺藩を助けた「れうし町」は城主から受けた特権によって、豊かな舞鶴湾を基盤に定住しながら漁を営むようになったようだ。それから約100年後。城下の絵図には「吉原町」と書かれ、建物もある。吉岡さんは「城下町が栄える中で海辺の民は市民権を得て、舞鶴のまちに溶け込んでいったのだろう」と話す。
京都の漁業の先駆者に
その後、江戸中期の1727年に城下町の半分を焼失した火災で吉原は火元とされ、城主から伊佐津川の対岸へと集団移転を命じられた。そして明治維新後、開拓精神あふれる吉原の人たちは荷揚げ場で魚が売れるようにして、魚問屋も作った。日露戦争が始まった明治37年には大阪への鉄道が開通。線路は舞鶴港まで引き込まれた。ブリや加工品を大消費地に売り込めるようになると流通や水産加工の会社も出資するようになり、「吉原水産合資会社」は京都府水産業界のトップランナーになった。明治34年に軍港ができて舞鶴湾で自由に漁ができなくなると、沖合漁業に打って出るようになる。

大正から昭和初期にかけて底引き網船や巻き網漁船を導入し、吉原は日本海域で有数の漁港に成長していった。舞鶴市水産課の原田直明さんは「ここぞという時に大きな投資ができたのは、水産業をいち早く組織化して流通の仕組みを築いたからだろう」と話す。
原型は、縄文時代の丸木舟!
吉原には今も昔の手こぎ舟が10隻ほど残っている。長さ2㍍の櫓と両脇にオール。3人力でこげるから「速舟」と呼ばれた。明治期には若狭湾の冠島にある老人島神社に参拝した後、島から吉原まで速さを競い合っていたという。シャープな船体が特徴だが、吉岡さんによると、そのルーツは大浦半島の浦入遺跡で発掘された6000年前の丸木舟に行き当たるという。8人ほどで航海できた縄文時代の高速船。丸木舟は直径1㍍を超える杉を石斧でくりぬいたものだが、確かに形は速舟そのもの。若狭湾岸には競漕舟を「マルキ」と呼ぶ地域まであるというのだから驚きだ。

丸木舟の性能は2019年に思わぬ形で証明された。人類学者や考古学者たちが取り組んできた「日本人はどこから来たのか」プロジェクト。台湾から沖縄・与那国島までの200㌔を3万年前のままの道具と技術で渡海する実験に、丸木舟が採用されたのだ。舞鶴市には2006年に市民と作ったレプリカの舟がある。彼らは2017年に舞鶴に来てレプリカの舟を浮かべ、若狭湾の冠島まで航海テストをした。チームはここで自信をつけ、見事に200㌔の海を渡ったのだった。
故郷のルーツを学ぼう
地元の人たちも埋もれた歴史に目を向け始めている。吉原にある築100年の銭湯「日の出湯」。家に風呂がなかった時代には、海で冷えた体を温める銭湯は欠かせない。夕暮れには土間に置いたテレビの前に50人ほどが塊になってプロレスを観戦していたという。近く国の有形文化財に登録される見通しで、今もご近所が集う。日の出湯を営む高橋一郎さん(72)は小学校の教師をしていたが、いつか、生まれ育った吉原の歴史を調べてみたいと思っていた。
幼なじみも先輩も、みんな年を取っていく。高橋さんは2020年7月に郷土史を学ぶ「やおちクラブ」を作った。地元の歴史を探り始めたところで今回の取材を受けた高橋さん。自分たちの先祖が田辺城の籠城戦に協力し城下町の一員となっていったこと、朽ちかけの舟が6000年前の丸木舟とつながっていること--。どれも驚きの連続だ。「もっと知りたい、調べたい! そんな気持ちになりました」。吉原小には創立100年の時に作った記念誌があり、分厚い付録がついている。後世に遺された資料だ。高橋さんは「創立150年まであと5年。世代を超えて学ぶ仲間の輪を広げ、みんなで記念誌の続きを書きたい」と話す。
城下の漁民・吉原の人々は京都の漁業のパイオニアだった。発展の原動力は海の民が受け継ぐ開拓精神にあるのだろう。吉原小の校歌には、こんな一節がある。「自治の旗を立てて進まん 友よいざ」。先人たちはこの歌にどんな思いを込めたのか。ルーツを探る旅が始まろうとしている。